NHKの「100分de名著」では、サン=テグジュペリの『人間の大地』を4回にわたって取り上げてきた。
サン=テグジュペリ“人間の大地” (4)人間よ、目覚めよ!
案内役はフランス文学者の野崎歓氏。
今回の第4回は、最終章である第八章「人間たち」がテーマとなった。
愛するということは「共に同じ方向を見ること」
番組冒頭で取り上げられた印象的な言葉に、サン=テグジュペリの有名な一節がある。
愛するということは、互いに見つめ合うことではなく、共に同じ方向を見ることだ
野崎氏はこれを、単なる恋愛に関することではなく、愛することは、ここでは、生きることを指すという。それは飛行士たちが飛行機に乗ると、同じ進行方向を見るのと、同じようなことだと。
サン=テグジュペリは操縦士の経験から、考えついたことなのだろうか。
時代を超えた批判と洞察
サン=テグジュペリは、ナチスの政策に対して痛烈な批判を加える。しかし同時に、当時の西洋諸国が抱えてた差別や排外主義に対しても厳しい視線をむけていた。彼は西洋による支配に抵抗する砂漠の民の中にも、品位や公正さを見いだしていたという。
野崎先生によると、このような視点は当時としては「反時代的」な考え方であったという。高貴な飛行機乗り、サン=テグジュペリの孤高が伝わってくる。
亡命と「星の王子さま」
フランスにドイツが侵攻し、サン=テグジュペリはアメリカに亡命することになる。アメリカには親ナチス派と、ナチスに抗うドゴール派が存在し、彼はそのどちらにも与しない態度を批判された。孤立したともいえる状況だった。
野崎氏は、そのため「もし亡命していなければ『星の王子さま』は書かれなかっただろう」と語る。フランスを抜け出したけれども、再びヨーロッパ戦線に戻る作者の人生は、あの作品と密につながっている。
興味深かったのは、野崎氏は自身の訳書では原書に忠実な「小さな王子」という日本語タイトルを採用しているが、ここでは「星の王子さま」という題名でこの作品を呼んでいたことだ。すでに日本の文化に根づいた呼び名だからだろう。
(ところで「人間の大地」の訳はいくつかあり、「人間の土地」というタイトルの本がある。野崎先生がフランス文学の道を選ぶのに大きな影響があったという堀口大學氏が訳者だ。番組でも机の上にこの「人間の土地」が置かれていた(宮崎駿氏の絵の本)。しかし野崎先生は「人間の大地」を採用している。これも面白い。)
「精神の息吹きを通わせること」
結びの一文に出てくる「精神の息吹きを通わせること」。この「精神」の原語は esprit。語源はラテン語の spiritus で、霊や精霊といった意味を持つという。野崎氏によれば、この一節には聖書の言葉が隠されているという。宗教的なニュアンスを含みつつ、人間の存在を根底から支える「息吹」を表していると考えると、重みのある結びとなっている。
怒りと希望、そして現代への響き
『人間の大地』には、戦争が避けられなかったことへのサン=テグジュペリの「怒り」が込められているという。しかし同時に、人間への信頼と希望も強く描かれている。
野崎氏は「今読むと、驚くほど(現代の世界情勢に即した)actualityにあふれている)」と述べていた。現在は、第二次大戦前と同じ状況だということ。この指摘が今回もっとも印象に残った。100分de名著のスタッフが、この本を今あえて取り上げた理由がそこにあるのだろうか。長くやっている番組なので、珍しくはないのかも知れないが、サン=テグジュペリの著作は「星の王子さま」に続いて2回目である。
戦争が起きるかも知れない時代。「人間よ、目覚めよ」とサン=テグジュペリは言った。
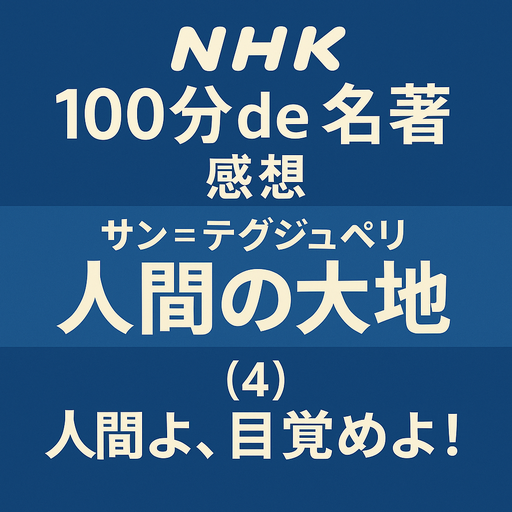


コメント