NHKの番組「100分de名著」は、1冊の著作を毎週25分、全4回で解説する番組だ。今回取り上げられている名著は、サン=テグジュペリの『人間の大地』。案内役はフランス文学者の野崎歓氏。
前回に続いて、第2回「惑星視点で見る」を視聴した。
惑星視点という新鮮な考え方
「惑星視点で見る」という発想が面白い。
サン=テグジュペリが飛行機で飛んでいた当時、人類史上もっとも高度の高い視点を得られるのは飛行機だった。(気球や飛行船はどうなんだろう・・・?) 人工衛星も有人宇宙機も、第二次大戦後に登場する未来の話なので、確かにそうだ。飛行機が単鳴る便利な輸送手段でなく、そういう道具であることに気付かされた。
当時の飛行機乗りが確かに「地球を見下ろす」存在だった。
飛行機から大地を俯瞰することで、その本当の姿を知ることができるというサン=テグジュペリの言葉には、現代では味わえない新鮮さがある。
今のようにインターネットの地図サービスで簡単に航空写真を見られる時代とは、全然違うんだ、と納得した。
それに関して、司会の伊集院氏が、普段は新幹線で通っている名古屋までの道を、自転車で走ってみると、いつもと違う感覚であったと述べた。自動車のほうが”低い”視点なので、サン=テグジュペリと逆の話になるのだが、伊集院光の話には納得できる。自転車のから見る風景は、車の窓から見るものと全く違うものだ。
サン=テグジュペリの不思議な体験
番組では、サン=テグジュペリが人類未踏の台地に降り立った体験が語られた。
アフリカ大陸という古くから人類が住んでいる大陸でさえも、この時代にはまだ人が足を踏み入れていない土地があったんだ、とびっくりする。
そしてそこに降り立った著者は、月面に降り立ったアポロ11号のアームストロングの心情と似通っていたのだと思った。
またアフリカがヨーロッパの国々の植民地となっていた時代で、住民が支配する国に従わない”不帰順地帯”というのがあることを知った。アフリカの歴史をもっと勉強しなければ、と思う。
アルゼンチンで招待された家での不思議な出来事についても触れていた。
この”動物好き”な2人の少女の話は、もっとディティールを知りたくなる。原作を読んで確かめたくなる。
想像の話なのだろうか? と思っていると見ていると、同じ思いなのか伊集院氏が「このエピソードは本当にあったことなんですか」と野崎先生に聞いた。野崎氏はニコッとした表情で「本当にあったと思う」と答える。
そのやり取り自体が印象的で、エピソードと、解釈の両方が心に残った。
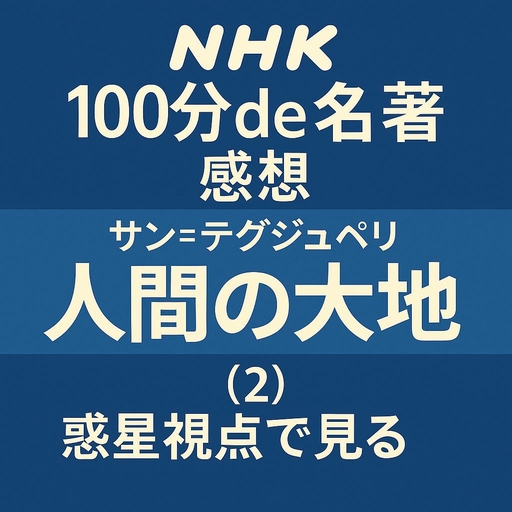
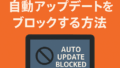

コメント